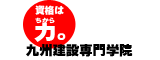合格者の声(合格体験談)
九州建設専門学院で学ばれ見事に「建築士」を取得された皆様から「お喜びの、感謝の、そして成功の軌跡」が毎日のように事務局に寄せられています。これらの合格体験談は、これから国家資格取得を目指される皆様の励みとなることでしょう。合格者の皆様、誠におめでとうございました。また、ご協力ありがとうございます。


建築のメンテナンスの会社に10年ぐらい勤務していました。建築の仕事をしたくて受験しました。会社時代はCADをやっていました。製図の勉強は学院に通い、毎日、2~3時間子供が寝た後の11時ごろから勉強しました。
学科の試験も大変でした。学院で勉強したことを家で復習するという毎日でした。学院で録音したテープを家で聞いていました。特に、構造は難しかったですね。計画や施工、法規はほとんど丸暗記です。勉強している頃は、睡眠時間が毎日4時間ぐらいで学院に2年間も通いたくないと思い、一所懸命に勉強しました。1年で合格できて、本当に良かったと思っています。


高校は普通高校で、今の職場も建築関係ではありませんので、全部1から勉強しました。学院のテキストと工業高校の教科書で勉強しました。両者はほとんど内容が同じでした。構造計算は難しくて、試験の時も計算問題の5、6題は諦めて、その代わり、他の問題でカバーするようにしました。
最初の年は、1日2時間ぐらいの勉捌寺問でした。社会人でも、2時間ならできそうだと思うでしよう。ところが、2時間では通りませんでした。2年目は1日3時間勉強したら、合格しました。建築はできればやりたかった仕事ですから、第2の人生は建築をやりたいですね。そんな夢を託して勉強しました。


30歳を越え、私も何か専門的な知識を身につけたくなって、建築士を受験しました。というのは、大学卒業後、しばらく住宅メーカーに就職していたのが動機になったような気がします。
一度でパスしたかったから、4ヶ月前から本格的に取り組みました。教科書を中心に勉強しましたが、意外と面白かったですね。べつに苦労した意識はありません。うまくいった方だと思います。
今度は1級にチャレンジするつもりです。2級で1級の感触をつかんだつもりです。


2ヶ月は集中して勉強しました。会社では不動産や、住宅のリフォームなどを担当していますが、多少、理解していたとはいえ、専門じゃないから、構造力学や、コンクリートなどの問題になると、もう分かりません。
じつは会社の社長から、2級建築士の試験を受けるように命じられました。というのは、免許を持っている人が、定年で辞められるので「つぎは、お前さんが試験を受けなさい」ということだったのです。喫茶店でくつろぐ時や、バーガーショップで昼をとる時も、わずかの時間も利用しました。


インテリアコーデイネーターの講習会を受けているとき、担当の先生から「受けてみたら」と勧められたんです。
というのは、私自身、建築士の試験にチャレンジしてみたい、と考えていたところなので、背中をポーンと押された感じでした。気がついたら、目標に向かって進んでいた、というところですか。
通信教育を利用して、テープを2度3度と聞いて勉強しました。、でも、ゼロからのスタートでしたから大変でした。図面が特に難しかったです。


建築関係とは仕事は全然関係ありません。ただ、将来、家を建てるとき、いろいろ知っていたほうが有利だろうというのが、受験の動機ですね。
知識はゼロですから、教科書を読んでも、分かるはずがないから、勉強方法を逆にしました。まず、問題集を1問やって、それから教科書のその部分を勉強しました。
問題を解く、というより、問題を解答といっしょに読む、とう方法でした。意外と、これが成功したのではないかと考えています。1問毎に、最初から、入念に読んだのがよかったのでしょう。


建築会社に入社して1年になります。大学は建築学科で、4年次の秋から日曜毎に学院の2級建築士コースに通っていました。でも、卒論が忙しくて中断。その後、入社し4月から再度日曜毎に通いました。本格的に勉強したのは5月からです。授業だけでは足りないので、平日の夜も練習問題や模擬問題を何回も解きました。それ以前はさほど緊張感もなく勉強していたのですが、それでも学生の頃から学院に通っていたから、本を読んでもある程度理解できました。やはり、働き出して勉強と両立するのはなかなか大変ですね。


建築・土木のコンサルタント会社に勤務しているのですが、仕事柄、資格が欲しくなり、学院の2級建築士コースに入学しました。週3回、学科2回、製図1回を受講しました。学院は試験の過去問題とかテスト形式をやってくれるので、大変助かりました。仕事で建築のことには一応、触れるのですが、本格的には今回が初めてで、構造計算などはやはり難しかったですね。
でも、本試験では学院でやった構造計算の問題と類似したものが出ていましたので、本当に良かったです。試験直前は、過去問題や苦手な問題を繰り返しました。


内装関係のCADオペレーターをしています。以前、勤務していた会社では、書店や店舗などの商業施設の内装設計をしていました。でも、内装関係ですから、建築全般とは別で、建築の基礎的なことは学院で教えてもらいました。やはり、独学では難しいですね。学院でひとつひとつ丁寧に先生が教えて下さったので、わかりやすかったです。
内装設計をしていましたので、計画や法規は少し理解できたのですが、構造計算や施工となると普段、接していないので大変でした。学院で詳しく教えてもらって、問題を何回も解いていたらわかるようになりました。


ステンドグラス工房をやっていたのですが、5年程前から、息子2人が意欲的でしたので、ログハウスの建設にも取り組んでいます。社名は(有)エトルリアです。ステンドグラスの打ち合わせとデザインを私が担当し、製作は女性スタッフ7人に任せています。ログハウスの建設は息子二人との共同作業ですが、北米産の丸太の皮剥きから製材、建設まで自分たちだけですから、年間2棟くらいが精一杯です。
でも、100戸以上のログハウスを、施工だけでなく、設計もやりたいとなると、どうしても2級建築士の資格が必要でしたので今回、挑戦しました。


大型ごみ焼却所や発電所のボイラーなども製作する造船鉄工所に勤めています。仕事上は、建築基準法が直接関係するわけではありません。ただ、大型ボイラーの周囲を鉄骨などで建家を組むことになり、重量のあるボイラーの基礎部分をどうするか、建家はどうするかなど、建築的な知識も必要になってきます。また、ボイラーを制御するのに、コントロールルームも必要になります。建築の基礎的な知識があれば、役立ちます。
私自身は工業高校を卒業して、一時、福岡の建築会社に勤務し、現場監督をしていたことがあります。その頃、2級建築士の資格は取得していました。その後、長崎に帰り、現在の会社に勤めた訳です。1級建築士の試験は、10年ぐらい前に独学で2回ほど挑戦したのですが、失敗し、中断していました。
今回、1級建築士を受験することにしたのは、後輩が受験したこともあったのですが、国の給付金制度が利用できることがわかったからです。この制度を利用すれば、ずいぶん助かります。また、他の学校と比べ、学院が安かったので、学院の通信講座に申込みました。受験資格は2級建築士を持っていましたので、問題ありませんでした。
ただ、1級に挑戦してみようと思い立ったのが遅く、4月の開講にやっと間に合った位です。それから3ヶ月位で学科試験でしたので今回は受かるとは思っていませんでした。今、二次試験の製図に向けて準備しているところです。製図作業そのものは、会社の日常業務のなかで、ボイラー鉄骨の詳細図や工作図などを書いていますので、それほど苦にはなりません。
ともかく、見識が広がれば周りのことも見えてきます。井の中の蛙になることもありません。手続きの違いを知れば、仕事にも役立ちます。今回本当にトライしてよかった思っています。


高校の頃から理数系コースで、建築の図面やモデルハウスを見るのが好きで、設計をやりたいと思っていました。短大で建築を学び、卒業後に建設会社に勤めました。今は、CADや手書きで図面を書いています。入社し2年ほど設計に携わり、2級建築士を取ろうと思い、学院に通いました。平日は仕事ですので、日曜日の午前と午後に分けて2級建築士とCADの講座を受講しました。2級建築士の資格とともに、CADの資格もとりました。
あと4年で1級建築士の受験資格が得られます。何とか合格して本格的な設計に取り組みたいですね。


高校を卒業し看護学校に通ったのですが、あまり適性がないと感じ、住宅メーカーに入社し設計課勤務になりました。それも積算部門の部署です。家の構造があまりわからないので、現場に連れていってもらい、火打ちだとか屋根伏せとかを実際に見せてもらい、数量のチェックの仕方やCADでの図面化を教えられました。
平成8年にインテリアコーディネーターを取りましたが、色彩計画も含め、もっと建築を知りたくて2級建築士にチャレンジしました。今は旅館、ホテル関係のコンサルタント会社に勤務していますが、常に学んでいたいですね。
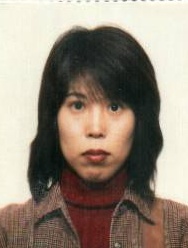
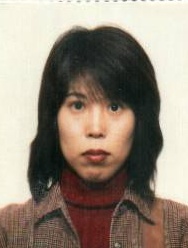
店舗設計に非常に興味があります。今はインテリア関係の会社に勤務し、インテリアコーディネーターの資格も持っていますが、住宅だけでなく、店舗設計にも関わりたかったのです。ところが、インテリアコーディネーターの資格はあっても、図面は書けるのかとか、建築士の資格は持っているのかなどと言われ、店舗設計に関われない。それならと思い、学院に通い、2級建築士にチャレンジしました。
今回、見事に合格したので、これから店舗設計に関わった仕事をやって行ければと思っています。将来は、商業関係の商業施設士の資格も狙っています。


大学は建築科を出たのですが、まったく違う分野に就職し、今はフリーで編集やライターをしています。ただ、仕事で高齢者問題に関わるうち、なぜ、今までの住宅はバリアフリーに取り組んでこなかったのか、憤りを感じました。自分の両親も高齢になり、それなら自分で資格を取ろうと思いました。1級建築士の友達に相談したら、本業が建築外なのだから2年掛かりでやったら、と忠告され、実際もその通りになりました。過去問題からすると、阪神大震災以後、試験問題は少しヒネってあるようです。製図も自己流で勉強するより学校で勉強した方が早道です。


工務店は、木造在来工法の注文住宅を中心にやっています。これまでは設計はよそに頼んでいましたが、自社で設計から施工までをするために、建築士の資格に挑戦しました。仕事をしながらの受験勉強ですから、どうしても仕事優先になり、時間の確保に苦労しましたが、問題を覚えるために自分でカードを作って、仕事中でも暇があるとそれを見て勉強する方法もとりました。
それと、学院で知り合った仲のいいグループで勉強会をしたりしました。みんなで励ましあい、刺激しあって、随分やる気をもらいました。


工務店は父が経営しています。仕事は木造の注文住宅が中心だから、2級建築士の資格を持っていた方がいいと思い、受験しました。勉強は学院の講義とテキストや問題集だけでやり、わからないところがあると、一緒に受験した友達と教えあったりしました。できれば、もっと数多く問題をやればよかったと思いました。
業界は今、着工件数が減って厳しいのですが、何とか頑張り、次に資格を取るとすれば、住宅建築の仕事をしているので、宅地建物取引主任者をとも考えています。
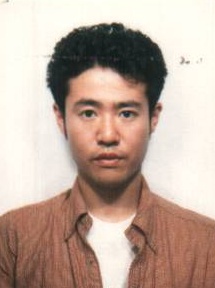
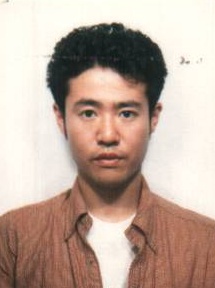
建築や不動産関係の仕事を考え、就職に有利になると思い資格取得を考えました。宅地建物取引主任者資格を1年前に取得しています。建築士の受験勉強をしているときは、勤めをやめていたので時間は十分にありました。
勉強は、学院の講義とテキストと過去問題集を買ってきて、3回ほど繰り返して解きました。というのも、受験のためにはできるだけ多くの問題に慣れていた方がいいと思ったからで、問題集を徹底してやりました。私の場合は、それが結果的によかったようです。


家が工務店をやっていますが、就職するにしても資格を取っていたほうがいいと思ったのが動機です。最初はCADに挑戦して1級を取得し、学院にも勧められて2級建築士も受験しました。対策は学院の講義とテキストを中心に取り組みましたが、仕事をしながらですから、勉強は夜中になりました。学科は範囲が広くて、覚えるところが多く、それに最初のころは勉強の仕方がわからなくて大変でした。しかし、地道にやるしかなく、わからないところは学院の先生や学院で知り合った大工さんに教えてもらったりもしました。


資格を持っていたら就職に有利になるのでは、と思って受験しました。学生時代に建築のことをちょっと勉強したことがあり、興味があったことと、以前、土木コンサルタント会社に勤めていたので、似たような部分があって建築士を選びました。受験勉強に入った時は会社を辞めていたので、時間はありました。学院のテキストと過去問題集も2回ほど繰り返してやりました。
毎日、少しずつでも勉強する習慣をつけ、わからないことや疑問があったら、その時すぐに調べるようにしたのがよかったようです。