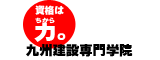合格者の声(合格体験談)
九州建設専門学院で学ばれ見事に「建築士」を取得された皆様から「お喜びの、感謝の、そして成功の軌跡」が毎日のように事務局に寄せられています。これらの合格体験談は、これから国家資格取得を目指される皆様の励みとなることでしょう。合格者の皆様、誠におめでとうございました。また、ご協力ありがとうございます。


白い紙の上に引いた線がだんだん具体化して形になっていく。そんな面白さ。もともと、自分の家は自分で建てたいなあ、と思っていたし、何かの足しになれば、というのが資格取得を思い立った動機です。勉強を始めたのは設計事務所に勤めていた頃でしたが、試験まで3ヶ月しかなく、時間がなく大変でした。学院の講義と講義のテープも活用しました。試験1ヶ月目前は仕事を家でして、勉強の時間を確保しました。家事や子供の世話、仕事に勉強と自分でも頑張ったと思います。
次は、設計製図試験に挑戦です。


鹿児島で設計事務所に勤めていたとき、CAD操作をやっていました。建築設計を自分でやってみたいと思ったのと、やはり資格を持っていた方が転職の時に有利になるのでは、と考えたのが受験の動機です。本格的に建築を勉強したわけでもなかったので、思い切って福岡に出てきて学院で学びました。
勉強は学院のテキストだけでしたが、わからない時は友達と教えあったりしました。普段はあまり一所懸命ではなかったのですが、試験の2週間前からは結構集中して、夜中の2時、3時まで勉強しました。


もともとはインテリアコーディネー夕ーになるのが目標で、建築や住宅全般を勉強するために建築士試験にも挑戦しました。当時、デパートに勤務していましたが、結構残業もあって講義に間に合わないことが多く、思い切って勤めをやめて勉強に集中しました。勉強は数学的な構造計算のところで苦労しましたが、学院のテキストと、出題傾向を見るために、過去問題集を買ってきて3回ほど繰り返してやりました。
現在では、インテリアの学校も卒業し、2級建築士を生かして目標のインテリアコーディネーターに向かって、準備中です。


試験は2度目の受験で合格しました。最初の時は、独学でしたからなかなか意思が続きませんでしたが、学院に通ってからは同じ目的の友達もでき、講義が終わって勉強会をしたり励まし合って勉強しました。当時、久留米市内の会社に勤めていたので、仕事が終わって福岡まで通学、自宅に帰るのは夜11時ごろになることもあり、大変でした。受験対策は学院の講義、テキストだけで乗り切りました。
受験の動機は、親が建築業で、私も学校は建築工業だったからです。いずれは1級建築士にも挑戦したいと思っています。


以前は電気工事の会社に勤めていましたが、建築に携わる中で設計の仕事をしたいと思い、建築士の資格に挑戦しました。会社をやめ、アルバイトをしながら学院に通いましたが、試験前1ヶ月はバイトもやめ、受験対策に集中しました。勉強は学院の講義、テキストが中心でしたが、過去の問題集を買ってきて、出題傾向を見たりもしました。日常の勉強のほか、問題をできるだけ多くこなしたのが、結果的にはよかったようです。
現在、建築関係の手伝いをしていますが、CADも扱っています。


前年に宅建を受けて合格。次はどうしようかな、と思っているとき、知り合いに建築士がいたこともあり、受験を思い立ちました。将来のことを考えて何か資格を持っていたほうがいいという思いや、自分を高めるために、というのが動機です。途中で仕事を代わったので、学院に通えなくなったのですが、その分、過去の問題集を買ってきて、3回ぐらい反復して取り組みました。夜9時ごろまで開いている図書館があったので、仕事が終わってそこに通って勉強しました。
いずれは資格を生かした仕事をしたいと思っています。


サービス、製造業に勤めていましたが、以前から建築に興味があったので、転職を考えて資格取得を思い立ちました。テキストだけでは不安だったのと、建築のことに慣れるために、建築関係の会社でアルバイトをしながら、学院の通信講座を受けました。勉強時間は結構ありましたが、試験前1ヶ月は酒の誘いも断って勉強しました。自分で決めた目標ですし、自分はこれに賭けていたので、半端な気持ちでなく、妥協しないで頑張りました。いずれは1級にも挑戦したいと思っています。


以前は建築関係の仕事に就いていましたが、建築士は仕事に必要な資格ですし、持っていれば役立つはずだからと思い、受験しました。会社をやめていたので、時間はたっぷりありました。勉強の苦労はあまり感じませんが、複雑な計算の構造のところでちょっと引っ掛かった程度です。学院での勉強のほか、問題集をやりましたが、これが役立ったようです。特に、試験前1ヶ月は、勉強してきたところの復習にあて、結構集中してやりました。
現在建築関係への就職を目指していますが、いずれ1級にも挑戦するつもりです。


会社は建設コンサルタント業で測量設計が主でしたが、建築も必要になり、主任技士の資格を得るために受験しました。残業も多くて、勉強は夜中になりましたが、学院の講義のほか毎日1時間でも、2時間でも参考書を広げるように心掛けました。建設といっても、分野が異なるためそれなりに大変でしたが、毎日少しずつ取り組んだのがよかったようです。
仕事をしながらの資格取得というのは、自分との戦いという面もあります。独学ではどうしても気持ちが萎えることがあり、結局は学校に通ったほうが早道のようですよ。


短大の時、インテリアを勉強しましたが、本格的に建築の仕事をするためには、国家資格の建築士を、と思って受験しました。勤めていた会社をやめ、受験対策に専念しました。やはり最初は専門用語に戸惑いましたが、学院でできた友達とわからないところを教え合ったり、情報交換。出題傾向をつかむため、問題集もやり、試験前1ヶ月は1日5時間ぐらい勉強しました。友達と会うときも参考書持参。暇があれば参考書を広げていました。周囲に「絶対合格する」と宣言、自分を追い詰めると同時に、協力もしてもらいました。


主人が1級建築士で建築設計事務所を開いています。私自身は建築のことはまったくわからず、主人の仕事を理解するためと、資格を持っていればいずれ何か手助けが出来るのではないか、と思ったのが受験の動機です。パートでの勤めですから、試験勉強の時間は確保出来ましたが、わからないところは主人にも協力してもらいました。勉強は学院の講義のほかは、過去10年くらいの問題集を何度も繰り返し、覚えるまで徹底してやり、試験前1ヶ月はとにかく、集中して勉強しました。いずれ主人と一緒に、仕事をしたいと思っています。


会社では、移動体通信などの中継基地などを建設する仕事をしていて、設計課に所属しています。大学では工学部の機械科でした。日常の仕事で設計というものになじんではいましたが、勉強のためということと、資格を持っていれば将来役立つだろうと考えて、受験したのが動機でした。勉強は、学院での講義や問題集が中心でしたが、特に試験の直前には過去の問題を集中的にやりました。
これから受験する人にアドバイスするとすれば、できるだけ多くの過去問題を解き、演習問題に慣れておいたほうがいいように思います。


以前勤めていた会社は、建築とは何の関係もありませんでした。将来は不動産関係、土地家屋調査士の資格を取りたいと思い、そのステップとして建築の基礎を学ぶために学院に通学しました。昨年の学科ともに受験は1回でパスしました。
前の会社をやめていたので、受験勉強の時間は確保できましたが、特に土、日曜は家族サービスも我慢してもらい、集中しました。受験対策は、過去問題をできるだけ多く解いて、問題に慣れるようにしました。2級にパスし、現在は建築会社に勤めています。次は、土地家屋調査士です。


受験は1回で合格しました。学校を出て、しばらくはコンピュータのシステムエンジニアをしていましたが、父が建築事務所をやっていたことから、建築士の道を考えました。普通科の出身ですから、まずは用語から苦労しましたが、学院の講義と、問題集で過去6~7年の出題傾向をつかみ、徹底してやりました。仕事をしながらの受験ですから、夜中の勉強になりましたが、仕事場でも受験仲間がいたので、いろいろ情報も交換しました。製図は父が演習をチェックしてくれるなど、協力してもらいました。まだ見習いですが、いずれは1級建築士に挑戦します。


20年間ぐらい、普通の企業で秘書をやっていました。技術を身につけたい、何か今までの生活とは違う分野のことをやってみたい、という思いで、学院の2級建築士講座に入学しました。製図なんかやったことなかったし、苦労はしましたが、身の回りの生活の中での建築を考えたことと、試験前は問題集で過去の出題傾向を、分野別に整理してひとつずつ潰していきました。会社を辞めて、受験勉強に集中できたことも良かったようです。
いずれは、建築関係の仕事につきたいと思っています。


仕事上必要な資格だったので受験したのが動機です。試験は6回目でパスしました。とにかく、時間がなくて、いかに早く書くかで苦労しました。仕上げの時間がないところは、展開を文字で説明し記入しました。試験は、どの範囲から出るのか分からないので、全般的にまんべんなく勉強しました。普段から線引きなど設計に対する基本的なことをきちんと習熟しておくことはもちろんですが、私は3ヶ月前から、学院から送られてきた資料をもとに30枚くらいトレースを仕上げました。


会社の業務は橋梁部門が中心で、既に1級土木施工管理技士は持っていました。建築部門の比率は低いのですが、大学の建築科を出ているので、最低持っておかなければならない資格、と思って受験しました。
試験勉強はほとんど出来なかったので、4回目でパスしました。試験問題は実務とはほとんど関係なく、パズルのようなもの。製図の経験がどうの、ということはなかったのですが、時間との勝負でした。だから、考えたとおりに出来るかどうか、パスしたのは、運のようなものでした。


資格を持てば仕事の幅が広がるし、有利だと思ったのが受験の動機です。設計製図の基本的な考え方は、日常の仕事のなかで慣れてはいましたが、手探り状態からの受験でした。というのも、同時に受験する親しい仲間がいなかったので、情報が少なく、不安がいっぱいでした。試験前はやはり、勉強の計画を立てて、集中して取り組みました。
設計製図は、自分が「書ける」というスペースに慣れておくこと。基本的なテクニックをきちんと覚えて、書けるようにしておくことが肝心ではないでしょうか。


2級は持っていましたが、周りが(資格を)持っているし、必要に迫られ1級を受験しました。会社に勤めていたときは、インテリアコーディネートを中心にやっていました。設計製図はプランニングが大きいので、苦労はしましたが、フリーになったときでもあり、ある程度、受験対策に集中できました。
私の経験からいうと、イマージネーションというか、感性の部分が大事で、普段から、サービスするスペース、されるスペースが、どうゾーニングされているかいろんなケースを見て実感しておくことが大切だと思います。


建設業という仕事柄、持っておきたい資格でした。5年前に1級土木施工管理技士に合格、建築士は6回目の受験で通りました。仕事は現場に出ることが多く、日曜日は学院で勉強という繰り返しで、大変でしたが、試験前は酒を断って受験勉強に集中しました。私は施工が専門なので、そういう意味では苦労しましたが、学院の資料を基にトレースを練習したりしました。
とにかく、短時間に書かなければならないので、設計の基本的な技術を身につけておくことが大事でしょう。